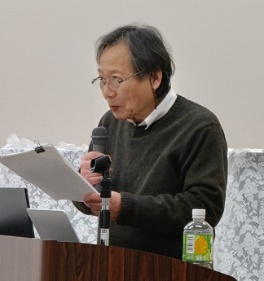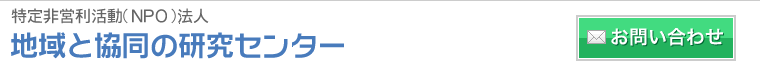【25.02.22】第21回 東海交流フォーラム 2
第21回 東海交流フォーラム 報告
第21回東海交流フォーラムの報告(2)を掲載します。
【特別報告「協同組合のアイデンティティ」話し合いの呼びかけ】
ICA(国際協同組合)ニューデリー総会を終えて 前田健喜さん(日本協同組合連携機構・JCA)
各分散会の紹介のあと、JCAの前田さんから報告がありました。ICAインド総会で何が決議され、JCAとしてどう対応するか、協議となったアイデンティティの改定案について説明してもらいました。特に、第7原則の地域社会(コミュニティ)への関与は、地域社会(コミュニティ)への積極的関与へと強める案となっており、協同組合は、事業を展開する地域社会の幸福とすべての人びとのために平和で公正かつ環境的に持続可能な未来のために活動すると、内容について説明されました。これから、考え合う場づくりをすすめていく予定です。
【地域懇談会別分散会「協同の一歩のふみだし方」
三重地域懇談会:多文化・多様な共生社会のひろがりに学ぶというテーマで分散会を開催しました。みんにこの西村先生、鈴鹿高専の学生二人も参加しました。三重地域懇談会の活動として2024年11月に岐阜の各務原市の「八木山ささえあいの会」を訪問したこと、外国をルーツとする住民1600人が暮らす四日市笹川地区で活動する「みんにこ」、そして、「みんにこ」と食品ロスの削減でつながった鈴鹿高専の学生も参加して、分散会で意見交換しました。
尾張地域懇談会:買い物からうまれた「班」とつながり、その過去、現在、未来というテーマで分散会を開催しました。生協の原点に立ち返ってみる、労働者協同組合の活動に注目する、様々な協同のありようを考えるなど、ワーカーズの藤井さんや参加者の活動や思いを出し合って意見交換しました。
三河地域懇談会:居場所の大切さを学び、考え、語り合うというテーマで分散会を開催しました。東海交流フォーラムに初めてリアル参加されたやなマルシェの加藤さんから、やなマルシェの現状を紹介いただき、三河地域懇談会世話人会からの報告(平和の学習会、えざね協同ファームや安城よこやまへ寄らまいかんなど)がありました。メインの報告は、NPO「ing」の松岡さんのお話です。参加者から質問も出され、居場所の大切さ、生協でのつながりなどが支えになったことを深めあうことができました。
岐阜地域懇談会:人と地域がつながる協同・ささえあい〜誰もがキーパーソン!?
というテーマで分散会を開催しました。八木山ささえあいの家の清水さんからは10月に岐阜地域懇談会が主催したプチフォーラムin岐阜の様子やそれ以降の活動の報告がありました。「私がキーパーソンとすれば キーパーソンのおかげでいっぱい喜びに出会える」という言葉が印象的でした。福井さんからは、生協の班のつながりが支えてくれた山県市でのサロン活動の様子が報告されました。井貝さんからは、ささえあいの家にあこがれて、瑞浪の地域で毎週開催のサロン「いなほ」の取り組みが紹介されました。みなさん、生協や研究センターというつなぐ場が一歩につながった、支えになったと思いが共有されていました。
【まとめの全体会】「現代社会における協同の意味を考える」
小木曽洋司さん(中京大学現代社会学部教授/研究センター常任理事)
小木曽さんは、「いっしょにくらしていくための方法」、それがつながるということであり、つながれば安心して、終の住み家として暮らしていける。地域で役立つ能力や知力は出会えなければわからない、出会ってはじめてわかる。家族に頼るには無理なので最終的には地縁となる。出会いで大切なのは、人を否定しないということ、違いがあるのでたくさん話すこと、はじめの一歩で何が大切か報告がありました。
東海交流フォーラムのまとめと第6期中期計画(2025〜2028)検討の呼びかけ
駒井義明さん(研究センター専務理事)
駒井さんはタリバンに追われて難民となりコープあいちで雇用されている方の動画を紹介しながら、報告がされました。私たちが住む地域には、一人暮らしの高齢者やシングルマザー、そして、紹介のような難民の方も住んでいる。生協が「大きな協同」として責任を果たそうとしているが、地域での私たちのはじめの一歩が大切であり、それが国際協同組合年のテーマにも重なるのではないかと、まとめがされました。地域と協同の研究センターの第6期中期計画は誰が主体かといえば、会員が主体で主人公であり、一緒に作っていきましょう、意見をくださいと呼びかけがありました。また、総会では、「小さな協同」をテーマに記念シンポジウムも予定していると報告がありました。
写真は上から 前田健喜さん(JCA)、分科会の様子、小木曽洋司先生。